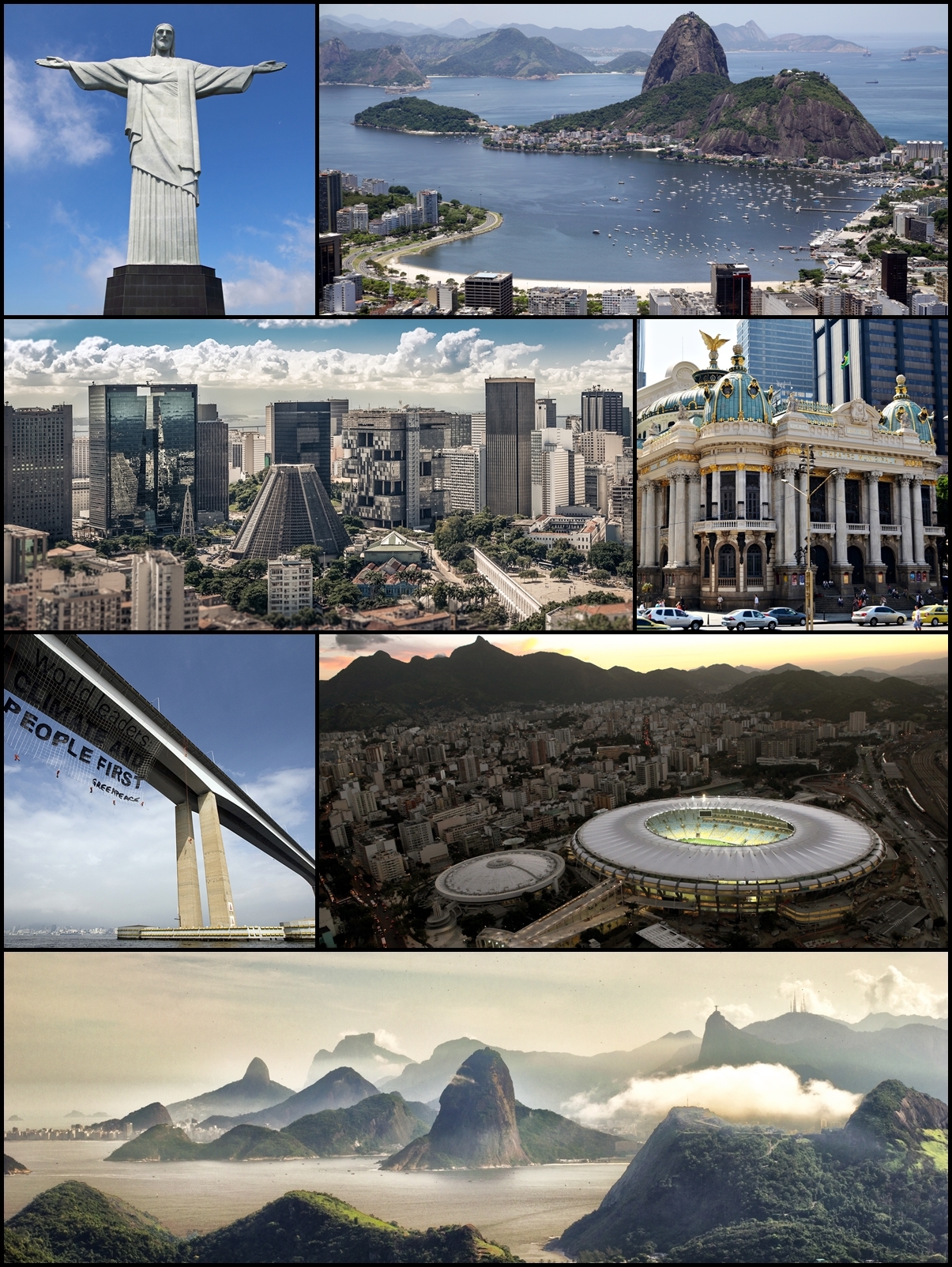昨日は、そんな彼らともう一人第二世代のインターンも交えて、渋谷で飲んできた。
インターンシップを終えたばかりの彼がどんな6か月を過ごしてきたのか、あるいはこれから現地入りする二人がどんなことを考えているのかを通じて、僕の9か月を振り返るきっかけとなった。
結論から言えば、話の最中でex-traineeである我々が何度も繰り返したから、少なくとも観念としては伝わってるものと思われるが、結局「楽しんだもん勝ち」である。
「何やりたいの?」と聞くと「マーケティング」とか「ロジスティクスに少しでも関わりたい」とかって返答がありがちで、ブラジルに行く前の僕も、わけもわからず恰好をつけるために似たようなことを言っていた。
しかし、そんなことよりも先に日々の生活の中で自分が何に無上の喜びを感じるのか、追求することの方が大事だ。
こう断言する理由は、いくつかあるが、何より学生インターン生の特権としての自由について書きたい。
一つは、インターン先企業との組織と個人の関係における自由。受入開始の段階で半年とか1年という期限付きで入ってくるAIESECインターンは、他の正社員・現地インターンと比較して、お客様として遇される面がどうしても出てきてしまう。それは期限付きなのだから経営の観点からすれば当然だ。しかしそれは逆に言えば、組織内部をじっくり見ることが出来るにもかかわらず、比較的何をしようにも自由ということと捉えることも出来る。もちろん給料をもらう以上は、給料を出す側が期待するアウトプット(仕事)をしなければいけない。しかしその仕事を追求することはきっと楽しいことだと思うし、学生身分を保留して(休学して)臨んでいる以上、学生をしながらのインターンシップとは緊張感が違うはずである。僕は、現にそうだった。
もう一つは、上記とも関連するが、現地社会における行動範囲の自由。こんなことに自覚的になってしまうのは日本人だからなのかもしれないが、アウトサイダーとして、または現地化を目指す一個人として、国籍は違えど同じ世代を生きる学生として、おじさんの話を聞きたくてわくわくしている一日本人学生として、などなど様々な顔で活動できる。これも前提として、一定の給料をもらい、学生身分から解放されていて、かつ会社化組織からも一定の距離感があるからこそである。
この自由に対して、もはや”特権的”という言葉を使ってもいいと思う。なぜなら、留学やらボランティアやらとの比較においても、或いは学生生活を終えてからにおいても、極めて珍しいものと推測されるからだ。だって、安定的にお金もらってる時点で学生としては珍しいし、一方で組織からの自由という意味でキャリアを歩み始めたら、あんな贅沢な時間の使い方はなかなか出来ないはずだからだ。
これから休学して海外企業でインターンシップに臨む全ての人に、そして我がインターン先に臨む二人に次の言葉を送りたい。
"Vivre - ce n'est pas respirer, c'est agir.(生きること、それは呼吸することではなくて活動すること。J.J.Rousseau)"
前途洋洋たる現地での生活を、存分に楽しんできてほしいです。